鮎原下花グループの皆さんと、保全隊役員共同で、コスモスの播種作業を行いました。


鮎原下花グループの皆さんと、保全隊役員共同で、コスモスの播種作業を行いました。

遊休農地の景観に配慮し、コスモスを植栽することにしました。保全隊役員総出で播種の準備作業を行いました。
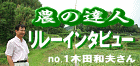
 さて第1回は木田和夫さん。エコファーマーとして環境にやさしい農業を実践する傍ら、産地直売所を立ち上げられるなど行動力も抜群。環境農業への思いは、ついに関西はじめてのJGAP協会指導員資格取得にまでも及ぶ。
さて第1回は木田和夫さん。エコファーマーとして環境にやさしい農業を実践する傍ら、産地直売所を立ち上げられるなど行動力も抜群。環境農業への思いは、ついに関西はじめてのJGAP協会指導員資格取得にまでも及ぶ。
木田和夫さんは今年60歳(2007年8月現在)。電気設備資材卸会社を3年前に早期退職。現在は認定農業者として農業に従事。この3年間にいちはやくエコファーマーの認定を受け,仲間と一緒に産直市場も立ち上げた。また最近は話題のJGAP(ジェイギャップ)の認定を受けるなど精力的に活動されている。
--16年9月に早期退職されて専業農家となった理由は何ですか?
農家の長男であるし、いつかは農業で身をたてたいと思っていました。またできるだけ早く地域に溶け込み、地域で生きて行きたいとも思っていました。幸いにも政府の農業改革が推進されていた時期とも重なり思い切って脱サラできました。 会社勤めの中で、会社オンリーではいけないと薄々感じていました。若いときは親に言われたことをやるだけであまり農業に面白みを感じませんでしたが、今は好奇心を持って農業に向き合っています。
--今は農業を楽しんでいるわけですね。
そう。楽しくてしかたがない。失敗しても再チャレンジすればいいという気持ちです。それに経験を積み重ねて、物事をきわめてエキスパートになれるという喜びもあります。
--退職して3年ということですが、どんな作物に取り組んでこられましたか?
1年目は主にレタス作りに取り組みました。私が会社勤めの間は家内が両親とレタス栽培をしてくれていたので、逆に家内に教えてもらう毎日でした。(笑) 今は栽培方法についても自分なりに工夫し、農薬・肥料・土の研究を重ねながら地元JAのレタス部会の役員をさせていただくまでになりました。
--木田さんは産直も立ち上げられていますね。立ち上げの経緯をお聞かせください。
農業で身を立てようと勉強するなかで、農業新聞等の情報から産地直売所に興味を持ちました。全国各地の実践例を目の当たりにし、自分でもやってみたくなり昨年仲間3人で産地直売所をたちあげました。
--直売所のPRをしてください
正式な名称は「ふるさと農産物直売所」です。現在約30名の会員がいます。会員は正会員と準会費で構成され、売上の一部を直売所に収めていただくシステムです。販売から二三日後には会員に売上額をフィードバックしています。
--産直は順調に見えますが
おかげさまで本年度の売り上げは今のところ去年の5割増しです。
--さてエコファーマーの認定を受けられた経緯をお聞きしたいのですが
脱サラして専業農家となった頃、地元農業委員の岩見倍夫さんより認定農業者へのお誘いを受けました。これから農業をやっていくなら環境保全型農業の認定農業者にならなければやっていけないよと。そこで普及所等にご相談をして手続きの方法等を教えていただき平成17年10月にエコファーマーの認定を兵庫県より受けました。
--まずは認定農業者となりその後エコファーマーをめざしたわけですね
 農業新聞を読んでいると、エコファーマー関連記事の出現頻度が高いんです。記事を追いかけるうち、自分でも環境や地球温暖化の問題などに興味を持ちました。これは自分もエコファーマーとなり実践していかなければならないなと考えました。
農業新聞を読んでいると、エコファーマー関連記事の出現頻度が高いんです。記事を追いかけるうち、自分でも環境や地球温暖化の問題などに興味を持ちました。これは自分もエコファーマーとなり実践していかなければならないなと考えました。
--エコファーマーの認定を受けるということはどんなことなのですか?
まず減農薬や化学肥料や農薬の低減に関する5年間の計画書類等を提出しなければなりません。書類審査を経て、「環境にやさしい農業にとりくむ農業者」であることを知事からお墨付きをいただくわけです。
--導入計画を実践していくわけですね。
形式的なものではなく、私自身環境に向けて努力しています。例えば、レタス栽培においてエコファーマーが実践すべき生産技術としては、化学肥料を低減するために有機質肥料や肥効調節型肥料の施用、あるいは化学農薬を低減するために雑草の抑制に役立つマルチ栽培や害虫防除の黄色灯やフェロモン剤を活用するなど、取り組むべき課題がたくさんあります。
--下集落にエコファーマーが拡がる機運はありますか?
現在集落内で営農組合を立ち上げておりますがエコファーマーの認定者は一人なのです。他に認定農業者のかたがエコの認定に向けて取り組もうとされています。一人でやるよりもまわりに広がってほしいと思います。例えばレタスの生産においても、長野県のレタス農家では、生産者団体全体でエコファーマーを取得するなどの例があります。環境のことを考えると範囲が広いほうがよいのです。
--集落や生産者団体にエコファーマーが広がりにくいのはどうしてでしょう
とにかくエコファーマーを実践するためにはハードルが高いのです。化学肥料をできるだけ使わない。かといって有機栽培は高くつく。農薬の使用量を低減すれば代替の対策をとらなければいけない。電気を使う、フェロモン剤、マルチを張るなど...費用の面で乗り越えなければならないハードルがいろいろあるのが原因でしょう。 その上、栽培履歴を日報につけなくてならない等、とにかく面倒くさいのです。外から見ると「自由にできない」農業に映るのかもしれません。
--それでもエコファーマーは広がってほしいのですね。
はい。仲間どうしの話題にもなるし地域の環境にも良いので今回の農地水環境保全事業のスタートにおいてもエコファーマーに取り組む場合二階建ての営農支援の追加助成がありました。何度か取り組む項目にいれることをすすめたのですが実現できませんでした。
--実際にエコファーマーのメリットは何でしょう
今のところ、直接的なメリットはあまりないですが地球環境や食の安全には貢献できるかと思います、できれば安全、安心なエコファーマーが生産した農産物が有利に販売できれば良いな~と思いますが消費者の認知が低いので難しいです。政府の支援ももっとお願いしたいと思います。
--生産物にエコファーマーのマークが使えるのですよね
でも産地直売所では使っていません。自分だけ貼るわけにはいかないし。それに社会的にはまだまだ認知されていないから。もちろんおいおい使っていきたいと思っていますが……。なにしろ説明が苦手だからなかなかエコファーマーをPRできない。(笑)
--主な販売ルートなど教えてください
JA、産直、直販(個人売り)飲食店、青果市場、仲買業者などあらゆるルートを活用しています。数値的にはレタスのウェートが大きいからJAの数字が大きくなります。産直の割合は売上としては少ないですよ。ほんのわずかです。
--産地直売所はそんなに儲からないというわけですか
会員のなかには家庭菜園的取り組みのかたもいるし、これが本業だという人もいる。順調に売上が伸びているし、淡路島の産直ではうまくいってるほうだと思う。やはり共同で運営すると難しい面もあることは事実です。将来は商品に農薬の履歴を読取る表示をしたり、商品補給をできるシステムづくりなど課題はいろいろあります。
--農場名は「木田ファーム」ですか?
まだまだ「木田ファーム」として商品を販売する機会は少ないです。これから直販で商品を売るときにこのブランドを使いたい。例えばメロンの直販に向けて準備しています。淡路島の旧一宮町では、ハウスメロンで成功しています。一個1500円から2000円の単価で販売されています。私も「木田ファームのメロン」を夢見てメロンの栽培をはじめたのですが、デジタル糖度計で計るがなかなか糖度が上がってくれない。(笑)今は栽培方法を試行錯誤している段階です。
--直販はブランド作りというわけですね
「木田ファームのメロン」をお待ちください(笑)まぁ。ブランド作りとまではいかなくても、例えば産直の仲間の中には、桃の直販に成功している人がいます。主にクチコミで広がり、宅配便を利用して全国に個人向けの販売をしています。 とにかく直販の割合を徐々に増やしていきたいと思っています。
--さてそろそろGAPの話をお聞かせください
 エコファーマーとくらべ、こちらはまだ歴史が浅く、日本国内で話題になりはじめてまだ2年程だと思います。JGAPの認定を受けるためには、農場の水質検査や肥料濃度を測定するなどひじょうに高度なデータが要求されます。
エコファーマーとくらべ、こちらはまだ歴史が浅く、日本国内で話題になりはじめてまだ2年程だと思います。JGAPの認定を受けるためには、農場の水質検査や肥料濃度を測定するなどひじょうに高度なデータが要求されます。
--エコファーマーどころではなさそうですね。(笑)
そうなんです。水質検査をやるのに、保健所も行きましたよ。土の検査の肥料濃度(ph)等は普及所で可能ですが。ほかにも測定項目がたくさんあります。残留農薬検査だけでも何十万とかかる。128項目の審査に合格してはじめて認定農場となるのです。
--こちらも認定マークがあるのですね。
GAPのマークはまだ流動的です。世界標準のEUREPGAP(ユーレップギャップ)と同等のJGAP(日本版)が世界基準に認められました。EUで使われているGAPのマークと日本のJGAPが制定したJGAPのマークがあります。JGAPのマークはまだ使えずに、世界共通のマークになるか検討中ということです。
--JGAP会員加入から1年経過しましたね
GAPはこれからです。外から見るとエコファーマーのほうが通りがよいです。今までかなり投資してきました。(笑)これも家族の理解があって実現したことです。もうやめようかと思ったことは何度もありましたが、これからの農業のためにはどうしても必要だと自分を奮い立たせてきました。
<<コラム>> 木田さんとJGAP
GAP とは「適正農業規範(Good AgriculturalPractices)」の略称。農業生産現場における安全性確保の具体的な対策として、世界的に普及しているルールです。そしてJGAPはこの日本版ともいうべきNPO法人です。またJGAPの理念を普及させるために認定指導員制度があり木田さんは今のところ関西初めての認定者。 JGAPの認証農場となれば、生産された農産物の安全性や品質を消費者にアピールすることができる。128項目の審査の後、是正項目をクリアーすれば晴れて認証農場となる。木田さんの場合、穀物と青果物の認証を得た。関西ではJGAP認証農場は少なく、先日読売新聞の全国版でも紹介されたほど。
--エコファーマーとGAPのつながりはどうとらえたらよいのでしょう
GAPは頂点 その枝分かれのひとつがエコファーマーだと思います。GAPがめざすところに向かいたい。
--エコファーマーからGAPへと、環境にやさしい農業への歩みは着実ですね。がんばってください。さて最後に農の達人として将来の夢をお聞かせください。
環境にやさしい農業がみんなに理解してもらえるように、できるだけのことをしていきたいと思います。 あと、「木田ファーム」の将来像としては、ちょうど立地が山の斜面になるので、ログハウスでも建てて、農道には木の柵を作ったりして、観光農園のようにしたいです。体験農園にも魅力があります。やりたいことはいっぱいあるけど命がいくらあってもたりません。(笑) それから下集落に対しては、農地水環境保全隊の活動にも協力しながら、農地やため池に昔ながらの生き物が蘇ればいいなと思います。子供の頃は近所の清流でモツ獲りもしたなぁ。きれいな自然を蘇らせて都会の人たちと交流ができる「ふるさと」であってほしいです。
--ありがとうございました。
平成19年6月23日午後、鮎原下生態観察会が実施されました。
午後1時過ぎには集落内よりたくさんの人たちが集まってくださいました。 鮎原下子供会のみなさん、父兄のみなさん、花づくりグループのみなさん、民生児童委員さん、また松久保先生がこられるということで地元鮎原小学校の生徒達と一緒に応援にかけつけてくれた教諭の方々、とにかくこちらが予想したよりもたくさんの方々が集まってくださいました。集会所(鮎原下安心コミュニティプラザ)の大広間はとたんに一杯になってしまいました。
大広間には、当日の雰囲気をもりあげるため、「生き物観察会」の横断幕や「ようこそ松久保晃作先生!」のたれ幕も前日に用意しました。模造紙にマジックで手書き文字、手作り感覚満天です。 また集落の子供たちに、できるだけ地元の農業資源に興味を持ってもらおうと「下地区のため池いくつある?」と題した白地図に下集落内のため池を色塗りした掲示物を用意しました。さらに農村環境整備センターの「田んぼの生き物調査」の子供向けマニュアルなどを印刷し掲示しました。
当日のプレゼンテーション資料は松久保先生が用意してくださいました。淡路島内で撮影された貴重な写真を中心にたくさんの写真をお見せくださいました。プレゼンテーションはWindowsXP標準のスライドショーを使い先生自らオペレーションしながらお話してくださいました。
定刻の午後1時半過ぎにはレクチャーがスタート。本日の進行役は鮎原下子供会役員の小林さんです。小学校の教諭をされている小林さんは3児の母で現在育児休暇中、忙しい子育ての合間に今回の観察会の準備にもかけつけてくださいました。
保全隊の木田一也(きだかずや)代表の挨拶のあと、いよいよ松久保先生のレクチャーがはじまりました。 海外取材時の興味深いエピソードなどを交えながら、里山でみられる爬虫両生類について写真を見ながら丁寧にご説明くださいました。淡路島には貴重な生物などいないなどと考えがちですが、実は夜行性の生き物が多く、みんなが眠っている間に活動していることなど、生き物の生態についてもお伝えくださいました。ただ昔はたくさんいた生き物が減少していることは確かで、希少生物に目をむけ保存していくことはやはり必要なようです。 レクチャーの後、松久保先生より、こんな意見がありました、「みんなおとなしいな。どうしたんだろう?」子供たちはこんなレクチャーに慣れていないのだろうか?きっと小学校の総合学習の時間では、気心が知れた先生方のサポートもあってもっと元気に質問がでるのかもしれない。今回は集会所でのお勉強ということでいつもとちがう雰囲気にとまどっていたのかも知れません。
大人の方々の反応も気になるところでしたが、松久保先生は随所に大人でも興味をひくような話題を織り交ぜてお話くださり、あちこちで感嘆のため息が聞こえていた。例えば「イモリとヤモリの違いをご存知ですか?ヤモリは屋敷を守るもの、イモリは井戸を守るもの」等など....知っているようで知らない知識の数々、たまにはこうして子供たちと勉強するのもいいものですね
定刻どおり約1時間あまりのレクチャーの後、みんなで記念撮影。
いよいよフィールドに出て調査をはじめました。当日までに数回の下見と、当日先生といっしょに下見をしてコースを決定しました。 集落中央部の農道を通り、集落ただひとつの河川をわたり、程なく井堰の水路も見ることができます。農道の両サイドには田植えが終わったばかりの水田が続きます。
その後集落の民家がかたまった場所を通り、山裾にむけて坂道を上がっていきます。
この日の見学予定のため池は2箇所、ひとつは山裾の民家のすぐ下にありますが、池の透明度も高く、池の堤もしっかりしていて子供たちの安全面の配慮から、先生にぜひここでお願いしますと強引にお願いしました。
この池では希少生物こそいなかったものの、オタマジャクシやカエル、イシガメなどを見つけて子供たちは喜んでいました。この頃にはレクチャーの緊張もすっかり解け、網やバケツ・双眼鏡を片手に走り回っていました。池の水面をみつめる大人の方々の目もいくぶん輝いているように見えました。 もうひとつの池はもう少し山間にはいりますが、田んぼの畦伝いに移動することができます。前もって池の所有者に見学の了解を得たところ、観察会当日にはあぜ道の草まできれいに刈ってくださいました。あらためて集落住民の方々のご協力に感謝いたします。
さて、あぜ道で松久保先生が声をあげました。なにか小動物が掘ったような穴をみつけ、「亀が産卵したのだろうか?モグラの穴かな?」ということで園芸用の移植鏝で掘ってみることにしました。残念ながらモグラの穴のようでしたが生態観察はすべての場面で好奇心を忘れないことが大事だよと、先生は伝えようとしてくださったのかも知れません。
程なく2つ目の池に到着、この池は水量は少ないけど、上部にはもう民家がなく、雑木林や竹林がすぐそこまで迫っている。カスミサンショウウオの成育にぴったりかもしれないと選択しました。水溜りのように水が残っているだけなので池のお鉢の中にみんながはいって観察できるのも面白い。 この池でも残念ながら希少動物は発見できなかったが、子供たちは今度こそ、めずらしい生き物をさがしてやろうとゴソゴソ池の中をかき回しはじめた。ゴソゴソ、ガサゴソ、小さな池で魚とり網が動き回ります。ヤゴはたくさんいるけどカスミサンショウウオの卵は.....
その後、行きの行程と同じコースを戻り、集会所に引き返しました。水分補給のあと、子供会を代表して5年生の高田龍生君が松久保先生にお礼の言葉を述べてくれました。「遠いところから来てくださり、貴重なお話をありがとうございます。」と元気のよいごあいさつ。心のこもったお礼の言葉に先生も感激されていたようです。
貴重な2時間はあっという間に過ぎていきました。なかなか書きつくせませんが生態観察会は無事終了いたしました。