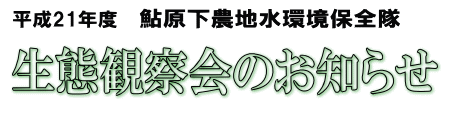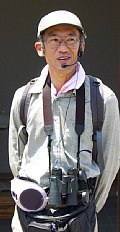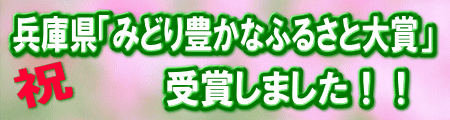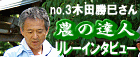山間地の維持管理ではじめた炭焼きがエコ暮らしの救世主に..
木田勝巳さん
(昭和22年3月21日生まれ平成20年9月現在満61歳) 取材日2008年9月6日
 木田さんは、元JA職員。JA勤務のかたわら父親と稲作・畜産・椎茸栽培等を営んでいた。昭和62年退職を機ににんにく栽培に挑戦したが、青森産や香川産のような立派なニンニクができずにやむなく断念。しばらくは従来からの酪農と和牛飼育に専念した。その頃はじめたのが山間地にあった自家の農地の維持管理のためにもなると考えた炭焼きであった。以来20年炭焼きを続けている。
木田さんは、元JA職員。JA勤務のかたわら父親と稲作・畜産・椎茸栽培等を営んでいた。昭和62年退職を機ににんにく栽培に挑戦したが、青森産や香川産のような立派なニンニクができずにやむなく断念。しばらくは従来からの酪農と和牛飼育に専念した。その頃はじめたのが山間地にあった自家の農地の維持管理のためにもなると考えた炭焼きであった。以来20年炭焼きを続けている。
先日は鮎原下農地水環境保全隊の生態観察会にご協力いただきましてありがとうございました。炭焼き小屋に子ども達が見学に来るようなことは今までございましたか?
問い合わせはありましたが、整備が不十分で実現しませんでした。
それでははじめての子供たちの見学だったわけですね。どんな印象を持ちましたか?
20年前に炭焼きを始めた当初は、変なことをしてるなというような目で見られていましたが、最近は炭の価値が見直されてきて各方面から注目されるようになりました。そんな中環境教育の観点からも小学生や幼稚園の皆さんに体験してもらえればよいなという気持ちがありましたので、その第1歩として今回の見学が実現しうれしく思っています。

さて炭焼きを始めた当初の話をお聞かせください。
はじめた当初は商品価値のある炭がなかなか焼けなかった。まさに失敗の連続でした。最初に取り組んだ炭は雑木中心でした。雑木を自分で切り出して自前の窯で焼きました。当時はあまりいい炭ではありませんでしたが、バーベキュー用として出荷できました。
最初から商品となったわけですね。
お蔭様で最初から捨てた炭はありません。炭焼きをはじめた当初から卸業者がついてくれたのも幸運でした。
当初、窯の作り方はどうして教わったのですか?
地元の年配の経験者に土窯の作り方を指導してもらいました。

木田さんの炭焼き小屋の土窯
販売ルートとしては卸販売が中心ですか?
卸販売も続けていますが、直販もしています。主に産直の物販所等で販売しています。
卸と直販の割合はどれ位ですか。
 ほぼ50:50です。卸は雑木の炭が中心で、直販は竹炭やウバメガシの備長炭を中心に販売しています。
ほぼ50:50です。卸は雑木の炭が中心で、直販は竹炭やウバメガシの備長炭を中心に販売しています。
木田さんの炭がほしいと思ったらどこで買えますか?
主に淡路島各地の朝市で販売しています。それから洲本市内の健康食品の店「夢ひろば」でも購入できます。また南あわじ市にある淡路ファームパーク イングランドの丘の入口にある産直でも購入できます。
生産者の表示はどうされていますか?木田さんの個人名ですか?
 三友商事というブランド名で販売しています。炭焼きをして販売を始めた当初三人の友人ではじめたからです。法人にはしていません。私は三友商事代表という立場です。
三友商事というブランド名で販売しています。炭焼きをして販売を始めた当初三人の友人ではじめたからです。法人にはしていません。私は三友商事代表という立場です。
島外では販売されてないのですか?
量が足りないのでほとんどは島内で販売しています。島外の方には、時折わざわざ買いにきてくださった方にお分けする程度です。
朝市・産直等で購入できるのはどんな種類の炭ですか?
販売スペースの関係もあり、竹炭のみです。
平成元年頃から炭焼きと販売を始められたということで、ちょうど20年が経過しましたね。
当初はバーベキュー用といった使われ方が多かったのですが、10年が経過した頃から竹炭を始めました。丁度エコが注目され始めた頃です。
竹炭はどんな使われ方をしていますか?
水の浄化や空気の浄化という観点で使われています。部屋の中の化学物質を吸収できるということから、部屋のインテリアの一部としても使われています。商品の展開も水や空気の浄化を意識したものが多いです。

竹炭を焼こうとするとどれ位の竹と日数が必要ですか?
一窯に2トン車2台分の竹を入れて、炭収は僅か600kgほどです。炭を焼き始めて3日ほど火をいれます。その後空気を遮断して4日ほどかかります。焼きあがった炭の中には良品というか秀品もあれば割れたものもあります。秀品は原形のまま浄化用として販売し、形が崩れたものは粉砕して農地に還元したり、床下の調湿剤として使います。
床下の調湿剤といいますと?
 割れた不良品などを粉砕して床下にいれます。炭は湿気が多いときは水分を吸ってくれて、乾燥している時は吸っている水分を放出してくれるんです。湿気の多い日本家屋に最適です。
割れた不良品などを粉砕して床下にいれます。炭は湿気が多いときは水分を吸ってくれて、乾燥している時は吸っている水分を放出してくれるんです。湿気の多い日本家屋に最適です。
面白い使い方ですね。どんなキッカケで利用されるようになったのですか?
最初は奈良県のお医者さんに使っていただきました。建坪100坪ほどの自宅を新築する際に、建物の基礎部分に直径1m、深さ1m50cmの円筒状の穴を25個ほど掘って、竹炭と備長炭を複合して投入しました。このお医者さんは電磁波も研究されている方で、調湿効果だけではなく有害な電磁波も遮断するということで炭を使いました。その後はクチコミで調湿剤として何度も床下に使われるようになりました。
床下調湿剤としてのコストは?
一坪に8リットルの袋10袋が必要です。1袋1000円前後で販売しているので、坪当たり1万円ほど必要になります。施工方法もコンクリートのベタ基礎に袋を並べるだけですので簡単です。
粉砕した炭を農地に還元するというのはどんな使い方ですか?
5月の田植え前に田んぼに鋤きこむのです。床下にいれる場合は粒が大きいが田んぼに入れる場合は粒を小さくします。
最近炭が高騰していると聞きますが?
それは原材料が少ないから。備長炭が特に不足している。一時は国内で消費される備長炭 の大半を中国に頼っていた。日本の業者が中国へ行って炭の焼き方を教えて逆輸入のような形で流通していたが、中国から日本への炭の輸出が禁止になってからは安価な備長炭が手に入らなくなった。
国内の備長炭の産地といえば?
和歌山。高知。北日本ではウバメガシが生育しない。ウバメガシでないと備長炭にはならない。
淡路島もウバメガシが多いですが最近はどうでしょう?
昔は多かったが、乱伐で禿山になってしまったところもあり水害のもとになったりして問題になった。竹の場合はたけのこが出て3年で切り出しできるまでになるが、ウバメガシの場合は芽が出てから20年はかかる。山林の保護のことも考えるとウバメガシがあるから切り出せばよいというものでもない。
さて最後に将来の夢をお聞きしたいと思います。
後継者もいないのであまり大きな夢は持っていません。竹林の荒廃を防ぐためにも、竹炭作りで竹の有効利用ができればよいなと思っています。

竹酢液も販売
増え続ける竹を集めて木田さんに焼いてもらうといった展開は可能ですか?
可能ですが竹炭の材料として重宝されるのは孟宗竹。鮎原下集落の竹林を見渡すと破竹と真竹が多いと思います。破竹と真竹は粉砕しか利用価値がない。孟宗竹は肉厚なので、水分の吸収量も多いので利用価値が高い。孟宗竹であれば運搬しやすいところから切り出して利用できます。 なにしろ、運搬や切り出しに人件費をかけることはできないのでアクセスを優先します。運搬しやすい場所であれば「孟宗竹が増えて困っているから切り出してほしい」と依頼いただいた場合、切り出した竹を原料として提供いただくだけでコストは一切かかりません。
実際、竹を切ってくれと言う依頼は多いのですか?
そこそこあるのですが、依頼があった分を全て切り出して炭焼きしても、それだけの炭を売りさばく販路が無いのです。販路が確保できれば焼ける。1ヶ月に一窯は可能です。
下集落全体で竹林の整備に乗り出そうという話になった時にはご協力願えますか?
地元のことだから協力しますよ。例えば焼いた炭を地元の相原川に伏せて水を浄化するなどすればよい。それが環境保全につながれば面白い。もちろん商品にもなりますよ。
炭焼きで食っていけますか?
 それは無理やな(笑)。農業の傍ら、小遣い儲けくらいになればなぁと思っています。
それは無理やな(笑)。農業の傍ら、小遣い儲けくらいになればなぁと思っています。